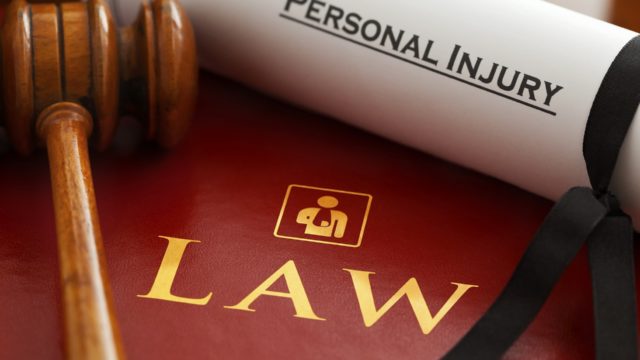フリーランスのための法律を元弁護士が解説!vol1
最近、ウェブライターの中にも「法律ライター」を名乗り、法律メディアや法律事務所からの依頼を受けて法律記事を書く人が現れています。
しかしこういった「一般の法律ライター」は、まったく法律の素養もないのに「自称」で法律を知っているというのみであり、非常に質の低い記事を納品される例も多数あるので注意が必要です。そもそも「一般の法律ライター」とう言葉自身が矛盾をはらんでいます。
今回は、「法律記事は法律資格を持った専門ライターに任せるべき理由」を、元弁護士の観点からご説明します。
1.「自称」法律ライターの蔓延
最近、ウェブライターという仕事も随分と世間に認知されるようになり、さまざまな分野のライターが現れています。
その中で私が気づいたのが「自称法律ライター」という、怪しい「一般ライター」の存在です。
弁護士や司法書士の先生方ならばご存知の通り、法律という学問は非常に難しく、本質から理解するのは本当に大変です。付け焼で把握できるものではありませんし、まして解説することなど不可能です。
ところが最近の「自称法律ライター」は、何の前知識もなく「相続入門」「離婚トラブルQ&A」のような本を読んだだけで法律をわかった気になり、適当な法律記事を書いて報酬を得ているのです。
こうしたいい加減な「自称法律ライター」が現れた背景には、法律記事への高い需要があります。
現在、ウェブ上には多数の法律メディアが現れています。一方専門家ライターはそう多くはありません。すべてに専門家ライターを使うことは困難なので、どうしても一般の「自称法律ライター」を使う結果となっています。法律事務所や法務事務所の需要も大きいです。
また、依頼側にライターや広告についての知識がないことも問題です。
弁護士や司法書士の先生方は、法律記事を必要としていますが「SEO」や「ウェブ記事」に不慣れで苦手意識を持たれているケースが多数です。
このような不知につけ込み、自称法律ライターは、品質が悪くても平気で「法律記事を書けます」「上位に持って来れます」「実績が高いです」「多くの法律事務所から依頼を受けています」などと宣伝してくるので、免役のない先生方はすぐに信じてしまいます。
しかし私はしょっちゅうネット内を見回っているから知っているのですが、ネットで活動している一般ライターのモラルの低さは尋常ではありません。私の知る限り、ツイッターでは自分の実績や収入などについて10倍、100倍、それ以上の嘘をついて虚勢を張るのが普通になっています。自称法律ライターには、見よう見まねで翻訳や法律記事の作成をしながら「英語よりも日本語の方が簡単だから、刑事訴訟法は余裕」などという、失笑しか得られないような自慢をしている人もいます(刑事訴訟法をウェブ記事で使うことはほとんどなく、明らかに嘘自慢です)。
このような低レベルの自称法律ライターの嘘に騙されてはなりません。
2.自称法律ライターは「非弁」に近いイメージ
自称法律ライターの一般ライターは、法律についての理解がないのに「法律記事を書けます」と言って適当な記事を書いています。
このことにより、ネット上にはいい加減で不正確な「法律記事」が蔓延しています。正しい情報を求めてネット記事を読む一般のユーザーにとっては迷惑でしかありません。
このような状況は、1種「非弁」に近いものと考えています。
非弁はもともと「弁護士ではないものが、いい加減な示談交渉などの法律行為を行うことによって一般の方に不利益を及ぼしてはならない」という考えによるものです。
また、次に説明しますが、こうした有害な自称法律ライターの料金は決して安くはありません。むしろ高いと言えます。昔からいる非弁業者も「弁護士に依頼するより安い」というイメージで困った人を取り込み、実際には弁護士より高い金額をとって跋扈してきた歴史があります。
このように、今、無資格で無責任な一般の「自称法律ライター」によって行われている高額かつ適当な記事のまき散らし行為は、非弁を彷彿とさせるものと言えます。
3.自称法律ライターは決して安くない
少し話に出ましたが、自称法律ライターの料金はどうなっているのでしょうか?
弁護士の先生方などは、法律記事を依頼されるとき「きっと弁護士や司法書士などの有資格者よりも一般ライターの方が安いはず」と考えるでしょう。実際、自称法律ライター自身もそのように宣伝して、法律事務所に入り込んでくるケースが多数です。
しかし実際には、一般ライターは決して安くはありません。
たった1000文字で10000円(単価10円)であったり、インタビュー、出張費用として数万円、記事代は別途数万円など、元弁護士の専門ライターである私よりもずっと高額な費用を取っている「自称法律ライター」もいます。
品質の低い記事を作成してもらうために、高品質な記事を期待できる専門ライターより高い金額を払うのは、ばかばかしいと思われないでしょうか?
4.結局書き直しが必要になってお金が無駄になる
弁護士の先生方が自称法律ライターに依頼すると、もう1つ大きなデメリトがあります。それは「使い物にならない記事」を納品されることです。
法律の素養のない人がいくら付け焼き刃で聞いたような言葉を並べても、それは法律的に意味をなしません。
また特に弁護士先生の場合、文章における「格調」も重要視されているはずです。法律事務所の記事に、あからさまに稚拙で適当な文章を載せることはできない、弁護士として恥ずかしいと思われないでしょうか?
私は、その感覚はとても重要なことと考えています。ホームページの文章は先生の「顔」です。一般の人にもわかりやすく、一方で法律のスペシャリストとしての格調高さも維持したいものです。
法律の言い回しがおかしくなっており、明らかに一般人が書いた文章など、」事務所のホームページに載せることはできません。
一般の「自称法律ライター」には、格調高くかつわかりやすい記事など、到底作成できません。平気で「これが一般の人にわかりやすい言葉です」などと言って、先生方から見たら「稚拙極まりない文章」を納品されます。そして高額な費用だけを請求されます。
実際、私の所に来られる先生は、そういう一般の「自称法律ライター」による被害を受けた方が非常に多いのです。
みなさま「一般のライターに依頼したけれど、ほとんどが書き直しになって自分で書いた方が早かった」とおっしゃいます。
「そのようなことであれば、当初から私の所にご相談に来られたら良かったのに」と心から思い、いい加減で自分のことしか考えていない自称法律ライターの跋扈する現状に悲しくなります。
5.専門ライターに任せるメリット
法律記事を依頼するならば、有資格の専門ライターを利用する方が、明らかにメリットが大きくなります。
以下でその理由をご紹介します。
5-1.リーガルチェックは基本的に不要
まず私のような元弁護士の法律ライターに依頼されるとき、リーガルチェックは基本的に不要です。私は50期代中盤の弁護士で10年程度の弁護士経験がありますから、法律については僭越ながら、一般の先生方と同等のレベルにあると考えています。
一般ライターに依頼した場合、リーガルチェックので相当な部分が使い物にならなくなりますし非常に手間がかかりますが、私に依頼していただけましたらそういった労力や無駄を一気に削減できます。
5-2.ほとんど修正が要らない
法曹資格のあるライターに法律記事を依頼すると、ほとんど修正が要らないこともメリットの1つです。
法律的な間違いはほぼ皆無ですし、少し表現を変えたいところを先生の方で書き足していただく程度でそのまま掲載できます。
また私は法律の素養だけではなく「SEO的な観点」も持ち合わせておりますし、キャッチコピーなどの広告の素養もありますので、おそらく先生達がご自身で書かれるよりも、広告用のウェブ記事として良質なものを作成できると考えております。
5-3.一般の「自称法律ライター」と比べて高くない
先ほど少し話に出ましたが、私のような法律の専門ライターの費用は、一般の自称法律ライターと比べて決して高くはありません。むしろ安いケースも多数です。同じ費用を払って一般のライターに依頼してほとんどの部分を苦労して修正するくらいなら、始めから知識のある専門ライターに依頼して楽にサイトを作っていった方がよほど良いことが明らかです。
5-4.安心して任せられる
先生方の事務所の重要な記事を依頼するとき、一般のライターに依頼するのは不安があるはずです。「どんな記事を納品されるのか?」と心配になるでしょう。
有資格でライターとしての実績も高い法律ライターであれば、そのような心配をせずに安心して依頼できます。
6.法律資格とSEOの両方を理解している貴重さ
ライター事務所HARUKAでは、元弁護士である私が全記事責任もって、先生方や御社のメディアの記事を仕上げます。
私は法律に対する深い素養があるだけではなく、SEOやSNS、MEOに対する理解も持ち合わせております。
これまで一般企業や商品紹介などのコピーライティングも多数経験してきたため、一般のユーザーに遡及するスキルも有しております。
このように、元弁護士として「専門知識」と「コピー、SEOなどの広告要素」の両方を理解しているライターは、日本広しといえども、控えめに言ってもそう多くい、むしろほとんどいないと考えております。
一般ライターは、所詮「広告」しかできないライターです。しかし広告的な視点のみでは法律の専門記事には対応できないのです。
弁護士や司法書士、法律メディアや不動産メディアなどで、法律絡みの記事を掲載されたい場合「一般の自称法律ライター」を利用すると多くの不利益を受けるリスクを伴います。
もし私に記事のご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。